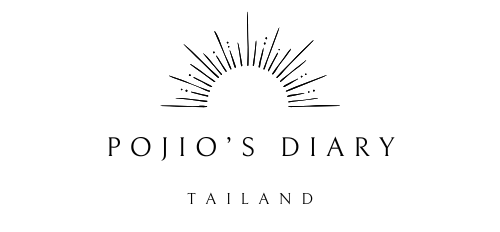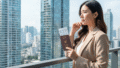タイ駐在のメリットについて関心をお持ちですね。タイは親日国として知られ、多くの日本人が生活していますが、海外赴任には期待と不安がつきものです。例えば、海外駐在になると給料は増えるのですか?という疑問や、具体的なタイ駐在員の年収はいくらですか?といった経済面での関心は非常に高いでしょう。
一方で、タイに住むデメリットや、海外赴任の落とし穴は?といった現実的な問題も無視できません。中には、準備不足からタイ移住が悲惨な結果となり、後悔するケースも耳にします。バンコクで快適にタイで暮らす日本人が多い反面、40歳からのタイ移住では仕事探しの壁に直面することもあります。また、老後の生活拠点として考えた場合の課題も存在します。この記事では、タイ駐在のメリットを多角的に解説すると同時に、知っておくべき注意点も合わせてご紹介します。 もうすぐタイ旅行!必需品リストはこちら
この記事でわかること
- タイ駐在で給与や手当がどの程度期待できるか
- 経済面以外(生活・医療・教育)の具体的なメリット
- 駐在生活のデメリットや潜在的なリスク
- 後悔しないために日本で準備しておくべきこと
タイ駐在のメリット:経済面と生活環境
- 海外駐在になると給料は増えるのですか?
- タイ駐在員の年収はいくらですか?
- タイで暮らす日本人の生活環境
- 40歳からのタイ移住と仕事
- 老後の移住先としてのタイ
海外駐在になると給料は増えるのですか?

多くの場合、海外駐在になると日本国内での勤務時よりも実質的な手取り収入は増える傾向にあります。これは、基本給に加えて様々な手当が支給されるためです。
主な手当には、海外での勤務自体に対する「海外勤務手当」や、赴任地の生活環境の厳しさ(治安、気候、インフラなど)に応じて支払われる「ハードシップ手当」などがあります。タイ・バンコクは比較的ハードシップ手当が低いか、対象外となる企業もありますが、海外勤務手当は期待できるでしょう。
さらに、経済的なメリットとして大きいのが、税金と社会保険料の扱いです。
税制面での優遇
1年以上の予定で海外赴任する場合、日本国内では「非居住者」扱いとなります。これにより、日本での住民税の納税義務が免除されます。(ただし、出国した年の1月1日に日本に住所があった場合、その年度分の住民税は納付が必要です。)
また、現地(タイ)で発生する所得税については、会社が負担してくれる「グロスアップ契約」を結ぶことが多いです。この場合、駐在員本人は、日本で勤務していた場合にかかるであろう税額(みなし税)だけを給与から天引きされるため、手取り額が大きく増える要因となります。
これらに加え、後述する家賃補助や子女教育手当なども加わるため、総合的な可処分所得は日本にいる時よりも格段に増加するケースが一般的です。
タイ駐在員の年収はいくらですか?
タイ駐在員の具体的な年収は、本人の役職、年齢、業種、そして所属する企業の給与規定によって大きく変動するため、一概に「いくら」と断言するのは困難です。
ただし、前述の通り、日本での基本給与をベースに各種手当が上乗せされる形態が主流です。例えば、タイの現地採用におけるマネージャークラスの給与相場が月額8万~12万バーツ(約36万~54万円 ※1バーツ4.5円換算)程度とされることがありますが、駐在員の待遇はこれを大幅に上回るのが通常です。
年収を押し上げる要因は、給与そのものよりも福利厚生(手当)にあります。
| 手当の種類 | 内容 |
|---|---|
| 海外勤務手当 | 海外で勤務することへのインセンティブとして支給される。 |
| 住宅手当 | コンドミニアムやサービスアパートの家賃を会社が全額または一部負担する。 |
| 子女教育手当 | 帯同する子供のインターナショナルスクールや日本人学校の学費を補助する。 |
| 医療保険 | 高額になりがちな現地の私立病院での医療費をカバーする海外旅行傷害保険などに会社が加入する。 |
| 一時帰国費用 | 年に1~2回、本人および家族が日本へ一時帰国する際の航空券代を支給する。 |
これらの手当は給与(現金)として支給されるものと、福利厚生(現物支給)として提供されるものがあります。特に家賃や学費といった大きな支出が会社負担となる点は、駐在員の可処分所得を押し上げる非常に大きな要因です。
タイで暮らす日本人の生活環境

タイ、特にバンコクは、世界的に見ても日本人が非常に暮らしやすい都市の一つです。2024年10月時点の海外在留邦人数調査統計によると、タイには7万人以上、バンコクだけでも5万人を超える日本人が在住しています。これは世界の都市別で見てもロサンゼルスに次ぐ規模であり、日本人コミュニティがいかに大きいかを示しています。
このため、以下のような環境が整っています。
1. 日本人街の充実
スクンビット通り周辺(プロンポン、トンロー、エカマイ地区)には「日本人街」が形成されています。日系のスーパー(フジスーパーなど)、日本食レストラン、居酒屋、書店、学習塾、美容室などが軒を連ね、タイ語が全く話せなくても日本語だけで生活が完結するほど便利です。
2. 食の選択肢
日本食レストランの数は非常に多く、そのレベルも高いです。また、ローカルなタイ料理の屋台やフードコートは安価で美味しく、多様な食文化を楽しめます。
3. 交通インフラ
バンコク市内はBTS(高架鉄道)やMRT(地下鉄)が整備されており、主要エリアへの移動が容易です。タクシーや配車アプリ(Grab)も安価に利用できますが、交通渋滞は深刻な問題点でもあります。
4. 医療レベルの高さ

バンコクにはJCI認証(国際的な医療機能評価)を受けた私立病院が多数あります。サミティベート病院やバムルンラード国際病院などでは、日本人専用窓口が設けられ、日本語通訳を通じて日本の医療機関と遜色ないレベルの医療サービスを受けられます。
日本人向けの教育機関も充実しています。バンコクとシラチャには日本人学校があり、日本の学習指導要領に沿った教育を受けられるため、帰国後もスムーズに日本の学校に適応しやすい環境です。また、インターナショナルスクールも選択肢が豊富です。
40歳からのタイ移住と仕事

「40歳からのタイ移住」を考える際、それが「駐在」なのか、現地で職を探す「現地採用」なのかによって、状況は大きく異なります。
駐在員として赴任する場合
駐在員は、日本の本社からの辞令(出向)であるため、年齢に関わらず、前述のような手厚い福利厚生やビザ(労働許可証:ワークパーミット)のサポートが会社から提供されます。仕事内容も日本での経験を活かした管理職や専門職であることが多く、キャリアの一環としてタイでの経験を積むことができます。
現地採用として移住する場合
一方で、40代からタイで現地採用の仕事を探す(移住する)場合は、一定のハードルが存在します。タイでは外国人が就労するためにワークパーミットが必要であり、その取得には学歴や職歴、そして企業側が支払う最低給与額の基準などがあります。
40代に求められるのは、主にマネジメント経験や高度な専門スキル(例:製造業の技術者、工場の管理職、IT専門職など)です。日本語のみで応募可能なコールセンターや営業職の求人もありますが、その場合の給与水準は、日本で同年代が得る給与よりも低くなる可能性が高いことは認識しておく必要があります。
駐在であれば年齢は武器になりますが、現地採用の場合は相応のスキルや経験がなければ、若い世代との競争で不利になる可能性も考慮しなくてはなりません。
老後の移住先としてのタイ

タイは老後の移住先(ロングステイ先)としても人気があります。これは「リタイアメントビザ(ノンイミグラントO-Aビザ)」という長期滞在ビザの制度が整備されているためです。
このビザを取得するには、満50歳以上であることに加え、経済的な要件(タイの銀行口座に80万バーツ以上の貯金がある、または月額65,000バーツ以上の年金収入がある、など)を満たす必要があります。※これらの条件は頻繁に変更される可能性があるため、常に最新情報の確認が必須です。
老後の移住先としてのメリットは以下の通りです。
- 温暖な気候: 一年を通して温暖で、日本の冬のような寒さがないため、体への負担が少ないとされています。
- 比較的安価な生活費: 日本食や輸入品にこだわらなければ、ローカルな生活を送ることで生活費を抑えることが可能です。
- 医療へのアクセス: 前述の通り、バンコクでは日本語が通じる高水準の私立病院を利用できます。
老後移住の注意点
メリットが多い反面、注意点もあります。最大の懸念は医療費です。外国人はタイの公的医療保険に加入できないため、高水準な私立病院を利用する場合、医療費は非常に高額になります。必ず民間の医療保険や海外旅行傷害保険への加入が必須です。また、ビザの条件変更リスクや、円安バーツ高による生活費の圧迫も考慮に入れる必要があります。
タイ駐在メリット以外の現実と注意点
- タイに住むデメリットとは
- 海外赴任の落とし穴は?
- タイ移住の悲惨な実態
- 後悔しないための準備
- 為替と物価上昇の影響
- タイ駐在メリットの総括
タイに住むデメリットとは
タイでの生活はメリットばかりではありません。駐在員であっても直面する可能性のある、現実的なデメリットや注意点が存在します。
1. 深刻な交通渋滞と運転マナー
バンコク中心部の交通渋滞は世界的に見ても深刻です。特に朝夕のラッシュアワーや雨季のスコール後は、車での移動時間が予測不能になることが日常茶飯事です。多くの駐在員は運転手付きの社用車を利用しますが、それでも渋滞に巻き込まれれば時間を浪費することになります。また、バイクの多さや現地の運転マナーの違いから、交通リスクは日本より高いと言えます。
2. 大気汚染(PM2.5)
特に乾季(11月~2月頃)のバンコクやチェンマイでは、PM2.5による大気汚染が深刻化する日があります。視界が悪くなるだけでなく、呼吸器系への健康被害も懸念されるため、この時期は空気清浄機の使用や高性能マスクの着用が欠かせません。
3. 「物価が安い」というイメージとのギャップ
タイの物価は、ローカルな屋台や市場を利用すれば確かに安いですが、駐在員が利用するような施設は例外です。
日本食レストランでの食事、日系スーパーでの輸入品(日本の食材や日用品)、高級コンドミニアムの家賃、インターナショナルスクールの学費などは、日本と同等かそれ以上にかかることも珍しくありません。「物価が安い国」というイメージのまま移住すると、想定以上の出費に驚くことになります。
4. タイ語の壁
日本人街や都心の高級デパート、私立病院では日本語や英語が通じることが多いです。しかし、一歩ローカルなエリアに入ると、タイ語でのコミュニケーションが必須となります。ビザの更新手続きなどで訪れる役所(イミグレーションオフィス)など、公的な場所では英語も通じにくい場面があり、言語の壁を感じることがあります。
海外赴任の落とし穴は?
タイ駐在に限らず、海外赴任には思わぬ「落とし穴」が存在します。これらは赴任者本人だけでなく、帯同する家族にも影響を及ぼします。
1. 世帯収入の減少(配偶者のキャリア中断)
赴任者本人の収入は増えますが、もし配偶者が日本で働いていた場合、そのキャリアを中断せざるを得ません。タイで配偶者が働くにはビザやワークパーミットの取得が必要ですが、駐在員の帯同ビザ(ノンイミグラントO)では原則就労できず、職探しも容易ではありません。結果として、世帯全体での収入が減少してしまうケースがあります。
2. 日本の資産に関する問題
赴任前に日本で購入した持ち家や車をどうするか、という問題があります。家を賃貸に出す場合、管理の手間やコストが発生します。売却する場合も、赴任のタイミングによっては希望価格で売れず、損失が出る可能性があります。
3. 日本の金融サービス利用制限
海外の「非居住者」になると、日本の証券口座での新規取引(株式や投資信託の購入など)が原則できなくなります。証券会社によっては口座の維持自体が難しい場合もあり、つみたてNISAやiDeCoといった資産運用を継続できなくなる可能性は、大きなデメリットと言えます。
4. 帯同家族(特に子供)への負担
子供を帯同する場合、現地の日本人学校やインターナショナルスクールへの適応がストレスになることがあります。また、配偶者も新しい環境でのコミュニティ構築や、慣れない言語・文化の中で生活することになり、精神的な負担を感じる場合があります。
タイ移住の悲惨な実態
インターネット上では「タイ移住は悲惨だ」といった声が見られることもあります。これらは多くの場合、十分な準備や計画なしに移住したケースや、駐在員であっても特定の環境に置かれた場合に起こり得ます。
駐在員の場合、生活面でのサポートは手厚い反面、仕事面での負担が非常に大きいことがあります。
データベース情報によれば、日本本社からの期待を背負い、現地法人の管理職として赴任するため、業務量が日本にいた頃より格段に増えるケースがあります。法律(36協定など)の適用外となることで、事実上の長時間労働が常態化することも考えられます。
また、タイでは「接待ゴルフ」や夜の付き合いも、重要な業務の一部として残っている場合があります。これが本人の意に沿わないものであった場合、大きな精神的苦痛となる可能性があります。
「仕事はキツイが、生活は天国」と言われることもありますが、その「仕事のキツさ」が許容範囲を超えてしまうと、「悲惨」な駐在生活になりかねません。これは赴任先の企業文化や本人の職務内容に大きく左右されます。
一方で、「移住」の文脈での「悲惨」な実態とは、リタイアメントビザなどで移住したものの、計画性のなさから金銭的に困窮したり、現地で病気になっても頼る人がおらず孤独になってしまうケースなどが考えられます。
後悔しないための準備
タイ駐在や移住で「後悔」しないためには、日本にいる間の準備が非常に重要です。メリットだけを見て判断するのではなく、デメリットやリスクを理解した上で対策を講じておきましょう。
1. タイ語の基礎学習
日本人街では日本語が通じるとはいえ、最低限のタイ語(挨拶、数字、簡単な日常会話)を学んでおくことを強く推奨します。タイ語が少しでも分かると、現地スタッフとの距離が縮まったり、ローカルな生活を安全に楽しめたりと、生活の質が大きく向上します。
2. 十分な貯金
駐在員であれば会社が生活基盤を整えてくれますが、リタイアメントビザでの移住を考えている場合は、ビザの申請条件(例:80万バーツの貯金など)を満たすだけでなく、急な出費や医療費、為替変動リスクに備えた十分な資金準備が不可欠です。
3. お試しでの短期滞在
もし可能であれば、観光旅行としてではなく、「生活する」という視点で1~2ヶ月程度滞在してみることをお勧めします。観光ビザ(またはノービザの30日間)を利用し、実際にコンドミニアムを借りるシミュレーションをしたり、ローカルな交通機関を使ってみたりすることで、旅行では見えない現実的な課題(暑さ、騒音、不便さなど)を体感できます。
為替と物価上昇の影響
タイ移住や駐在生活における最大のリスクの一つが、為替変動と現地の物価上昇です。
かつては「タイの物価は日本の3分の1」と言われた時代もありましたが、現在は大きく状況が異なります。特にここ数年の急速な円安バーツ高は、日本円の価値を大きく目減りさせています。
駐在員の場合、給与の一部が現地通貨(バーツ)で支給されたり、為替変動を考慮した調整手当が出たりすることが多いため、影響は限定的かもしれません。しかし、日本の銀行口座に貯めている円資産の価値は、バーツ建てで見ると減少していることになります。
リタイアメント生活者など、日本の年金や貯蓄(日本円)をタイバーツに両替して生活している人々にとって、円安バーツ高は生活費の圧迫に直結します。以前と同じ日本円を送金しても、手元に残るタイバーツが減ってしまうため、生活レベルを落とさざるを得ない状況も発生しています。
さらに、タイ国内のインフレ(物価上昇)も続いています。スターバックスのコーヒーやユニクロの衣料品、日系の飲食店などは、すでに日本よりも価格が高いケースが珍しくありません。この傾向は今後も続くと予想されるため、経済的な余裕を持った計画が不可欠です。
タイ駐在メリットの総括
タイ駐在のメリットとデメリット、そして後悔しないための注意点を解説しました。最後に、この記事の要点をリストでまとめます。
- タイ駐在の最大のメリットは経済面の手厚いサポートである
- 海外勤務手当やハードシップ手当により給与が増加する
- 家賃補助や子女教育手当が福利厚生として支給されることが多い
- 住民税の免除や現地税の会社負担により手取りが増える
- バンコクには5万人以上の日本人が在住している
- 日本人街が発達しており日本語だけでも生活が可能なエリアがある
- 日本語が通じる高水準の私立病院があり医療面で安心できる
- 40代の駐在は問題ないが現地採用での移住はスキルが求められる
- 老後移住にはリタイアメントビザ制度がある
- ただしビザの条件変更や高額な医療費には注意が必要
- デメリットとして深刻な交通渋滞と大気汚染(PM2.5)がある
- 「物価が安い」は過去の話で輸入品や日本食は高い
- 配偶者のキャリア中断による世帯収入の減少リスクがある
- 日本の金融サービス(証券口座など)の利用が制限される
- 為替変動(円安バーツ高)が生活費を圧迫するリスクがある