タイへの移住が決まると、まず気になるのが「何を持って行けば良いのか」という準備の問題です。とくに初めて海外で生活する方にとっては、現地で手に入るものと日本から持参すべきものの見極めが難しいかもしれません。本記事では、タイ移住のための必需品を中心に、実際にタイ赴任の際に持って行ってよかったものや、タイで手に入らないもの、日本にあってタイにないものを整理して紹介していきます。
また、現地で人気の高いタイで人気の日本製品や、現地で調達が難しく、日本から送ってほしいものにも触れながら、無駄のない荷造りをサポートします。
さらに、アルコールの持ち込み制限や、タイに入国するとき、現金はいくら必要か、タイに入国するとき、ダメなものは何か、といった入国関連の実務的な注意点についても、事前に知っておくことでスムーズな入国を実現できます。
記事後半では、タイ出国カード・入国カードの書き方についても具体的に解説します。これからタイでの生活を始める方、あるいは一時帰国を予定している方にとっても有益な情報を網羅していますので、ぜひ最後までご覧ください。 もうすぐタイ旅行!必需品リストはこちら
タイで本当に必要な持ち物と不要な物の見分け方
日本から持参すべき日用品や調味料の具体例
タイ入国時の制限や必要な現金の目安
入国・出国カードの記入方法や注意点
タイ移住必需品の基礎知識と持ち物選び
タイ赴任に持って行ってよかったものとは
日本にあってタイにないものリスト
日本から送ってほしいもの一覧
タイで人気の日本製品まとめ
タイ赴任に持って行ってよかったものとは
 タイ赴任の際には、生活必需品の選定がとても重要です。特に、現地での生活に慣れるまでの初期段階では「日本から持ってきて正解だった」と感じるアイテムが、日常のストレスを大きく減らしてくれます。
タイ赴任の際には、生活必需品の選定がとても重要です。特に、現地での生活に慣れるまでの初期段階では「日本から持ってきて正解だった」と感じるアイテムが、日常のストレスを大きく減らしてくれます。
なかでも持参して良かったとされる代表的なものには、医薬品・調味料・日用品が挙げられます。これらは現地でも手に入る場合がありますが、価格が割高だったり、品質や使い勝手が日本のものと異なるため、持って行く価値があります。
例えば、常備薬に関しては、風邪薬・酔い止め・下痢止め・目薬など、日本で普段使い慣れている薬を用意しておくと、体調を崩したときにも安心です。タイの薬は効き目が強めな傾向があるため、日本人には合わないと感じるケースもあります。
調味料についても同様です。タイでは日系スーパーでポン酢や醤油などを購入できますが、日本の倍近い価格になることも珍しくありません。麺つゆや白だし、みりんなどは、賞味期限の範囲でまとめて持参するのがおすすめです。
さらに、日本製のラップ、歯ブラシ、水に流せるおしりふき、アルコール除菌ティッシュなどの日用品も、品質が高く使いやすいため、多くの人が「持って行ってよかった」と感じるアイテムです。特に日本製のラップはタイの製品に比べて圧倒的に切れやすく、食品保存のストレスを軽減します。
このように、生活の中で「ないと困る」と思う物を見極め、現地で代替が難しいものを優先的に選ぶことが、赴任準備の成功につながります。
日本にあってタイにないものリスト
タイの都市部では多くの日本製品を見かけるようになりましたが、それでも現地で入手困難な物は少なくありません。特に、価格面や品質面で妥協せざるを得ない商品は、事前に把握しておく必要があります。
代表的な例として、「日本の生理用品やおりものシート」が挙げられます。タイにもJapan Qualityと書かれた商品は存在しますが、使用感や吸収力が日本の製品と比べるとやや劣ります。特に、おりものシートはサイズ感や素材の違いから、長時間快適に使い続けることが難しいと感じる人もいます。
「高機能な掃除用品や除菌関連製品」も入手しづらいアイテムのひとつです。日本で人気のウタマロ石けんやスクラビングバブルの替えブラシなどは、タイでは流通が少なく、仮に見つかっても非常に高価です。掃除のストレスを減らすためにも、必要なものは事前に準備しておくのが得策です。
また、「健康管理に使う特定の医薬品や健康補助食品」についても注意が必要です。風邪薬や整腸剤などはタイでも購入可能ですが、普段から服用している日本の市販薬や処方薬がある場合は、医師の許可を得た上で多めに持参すると安心です。特に子ども向けの医薬品は、現地では種類が限られています。
一方で、現地で問題なく手に入るものもあります。例えば、洗濯洗剤や柔軟剤は、硬水に合わせて作られているタイ製品の方がむしろ効果的です。このように、タイで買うべき物と持ち込むべき物を分けて考えることが、現地生活を快適にするための鍵になります。
こうした情報を事前に把握しておくことで、タイでの生活準備に無駄がなくなり、余計な出費や不便さを避けることができるでしょう。
日本から送ってほしいもの一覧
 タイ生活に慣れてくると、現地で手に入るものとそうでないものが徐々に見えてきます。その中で「日本から送ってもらって助かった」と感じるものは少なくありません。とくに、日々の生活でよく使う消耗品やこだわりの品については、帰国時の持ち帰りや家族・友人からの発送で補うケースが多くあります。
タイ生活に慣れてくると、現地で手に入るものとそうでないものが徐々に見えてきます。その中で「日本から送ってもらって助かった」と感じるものは少なくありません。とくに、日々の生活でよく使う消耗品やこだわりの品については、帰国時の持ち帰りや家族・友人からの発送で補うケースが多くあります。
まず挙げられるのが、「医薬品類」です。普段から服用している頭痛薬、胃腸薬、アレルギー対策の薬などは、成分や効き目に慣れているため、同じものを補充したくなる傾向があります。現地にも薬局はありますが、成分が異なる場合もあるため、日本製の薬を送ってもらうと安心です。
次に、「スキンケアやコスメ用品」も多くの人が送ってもらっているアイテムのひとつです。日本で販売されている敏感肌用や無香料タイプの商品は、タイでは手に入りにくく、仮に輸入されていても価格が数倍になるケースもあります。愛用しているメーカーの化粧水や日焼け止め、メイク用品などは、切れる前に補充しておきたいものです。
「食料品・調味料」も代表的な送ってもらいたいアイテムです。インスタント味噌汁やレトルト食品、乾物などは軽くて保存も効くため、スーツケースや小包の隙間にも入れやすい品です。なかでも、無添加の調味料やだしパックなどは、日本の家庭の味を支える大切な存在です。
また、子育て中の家庭では、「子ども用品」も多くリクエストされます。日本語のドリルや絵本、文房具、キャラクターグッズなどは、学習や遊びの幅を広げるために役立ちます。特に100均アイテムは、質が高く、遊びにも学習にも応用が利くため、まとめて送ってもらうと重宝します。
このように、現地では手に入らなかったり、割高だったりするものについては、信頼できるルートで日本から送ってもらう体制を整えておくと、長期滞在中でも快適な生活を維持しやすくなります。
タイで人気の日本製品まとめ
タイでは日本製品に対する信頼度が高く、多くの日本ブランドが現地でも高く評価されています。特に、品質・安全性・使い勝手の良さを重視するタイの消費者からは、日本製品が“確かな選択”として支持され続けています。
食品カテゴリでは、「即席麺、カレー、調味料」などが特に人気です。日本のカップラーメンは、スープの味や具材のバリエーションが豊富で、日本食ブームの影響もあり高い評価を受けています。ポン酢や白だしなども、日本食レストランや家庭料理に欠かせない調味料として需要があります。
日用品の中では、「歯ブラシ、ラップ、スポンジ、洗剤」などの家庭用品が広く愛用されています。とくに日本製のラップは“切れ味”と“粘着力”の両立が好評で、タイ国内で代替品が見つからないという声も多いです。また、日本の洗剤は抗菌性や香りが控えめで使いやすく、清潔志向のユーザーに人気です。
ドラッグストア商品では、「目薬、絆創膏、風邪薬、除菌グッズ」などが注目されています。日本の医薬品は信頼性が高く、特に敏感肌向けの絆創膏や、目の疲れに効くクールタイプの目薬は定番人気です。現地で販売されている製品と比べてマイルドな使用感も支持されています。
さらに、美容カテゴリでは「フェイスパック、化粧品、美容家電」の日本製品がSNSでも話題になることがあります。大量入りのフェイスマスクや日本ブランドのコスメは、お土産やギフトとしても人気があり、日系デパートやドン・キホーテでは特設コーナーが設けられていることもあります。
このように、タイでは日本製品が幅広いカテゴリで需要があり、品質重視の傾向が強まる中、今後も支持され続けると予想されます。
タイ移住必需品と入国・税関の注意点
アルコールの持ち込み制限とは
タイに入国するとき、現金はいくら必要ですか
タイに入国するとき、ダメなものは何ですか
タイ出国カード・入国カードの書き方ガイド
荷造り前に確認すべき注意ポイント
アルコールの持ち込み制限とは
 タイへアルコールを持ち込む際には、法律で定められた制限があるため、出発前に必ず確認しておく必要があります。知らずに超過してしまうと、空港で没収されるだけでなく、罰金が科される可能性もあるため注意が必要です。
タイへアルコールを持ち込む際には、法律で定められた制限があるため、出発前に必ず確認しておく必要があります。知らずに超過してしまうと、空港で没収されるだけでなく、罰金が科される可能性もあるため注意が必要です。
タイ入国時に個人が持ち込めるアルコール飲料の量は、最大で1リットルまでと定められています。この制限は、ワイン・ウイスキー・日本酒など種類を問わず、アルコール度数の違いにもかかわらず一律です。
例えば、ワイン1本(750ml)とウイスキー200mlを1本ずつ持ち込むようなケースでも、合計1リットルを超えると違反になります。また、複数人で入国する際も、各人ごとの制限が適用されるため、1人1リットルを超えないようにそれぞれ分けて持ち込むのが原則です。
空港の免税店で購入した場合もこの制限は変わりません。つまり、「免税で買ったから大丈夫」と考えてしまうと、入国時にトラブルになる可能性があります。現地の税関では、バッグの中身を開けて確認されることもあるため、正確な知識が求められます。
一方で、タイ国内ではビールやウイスキーをはじめ、さまざまなアルコール飲料が比較的安価に手に入ります。そのため、特別な記念酒や好みの銘柄など、現地で代替できないものだけを厳選して持ち込むのが現実的です。
このように、アルコールの持ち込みには法的制限があるため、荷造りの際はリットル数をしっかり確認し、トラブルを未然に防ぐ工夫が必要です。
タイに入国するとき、現金はいくら必要ですか
 タイに入国する際に所持しておくべき現金の額は、入国目的やビザの種類によって異なります。ただし、観光ビザやビザなしでの短期滞在であっても、タイ政府は入国者に対して一定額以上の現金所持を義務付けている点には注意が必要です。
タイに入国する際に所持しておくべき現金の額は、入国目的やビザの種類によって異なります。ただし、観光ビザやビザなしでの短期滞在であっても、タイ政府は入国者に対して一定額以上の現金所持を義務付けている点には注意が必要です。
具体的には、観光目的で入国する場合、一人あたり最低20,000バーツ相当(約9万円前後)、家族単位では40,000バーツ相当(約18万円前後)の現金を所持していることが求められています。この金額は、あくまで「提示を求められた際に見せられる現金」として必要であり、実際に使わなくても問題ありません。
これは、不法就労や滞在目的の虚偽申告を防ぐために設けられている措置です。タイ入国審査官の判断によっては、所持金の提示を求められるケースがあり、提示できなかった場合には入国を拒否される可能性もあります。
一方、クレジットカードやデビットカードの所持だけでは不十分と判断されることもあるため、現金(もしくは現金同等物)の携帯が基本となります。なお、これらの金額は通貨での換算が必要となるため、バーツで持参するほか、日本円や米ドルを携帯し、現地で両替できる準備をしておくのも一つの方法です。
さらに、長期滞在ビザ(リタイアメントビザ、就労ビザなど)の場合、現金の持ち込みよりも預金残高証明書や就労先の書類提出などのほうが重視される傾向があります。
いずれにしても、短期滞在者であっても「いくらかの現金を必ず持参しておく」ことが、トラブルを避ける最も確実な方法です。空港で提示を求められることは稀ですが、万一に備えてルールに沿った準備をしておきましょう。
タイに入国するとき、ダメなものは何ですか
 タイへ入国する際には、法律で持ち込みが禁止されている物品や制限されている品目が存在します。知らずに持ち込んでしまった場合には、罰金や没収の対象になるだけでなく、場合によっては入国拒否や刑事罰が課されることもあるため、事前に確認しておくことが非常に重要です。
タイへ入国する際には、法律で持ち込みが禁止されている物品や制限されている品目が存在します。知らずに持ち込んでしまった場合には、罰金や没収の対象になるだけでなく、場合によっては入国拒否や刑事罰が課されることもあるため、事前に確認しておくことが非常に重要です。
まず、絶対に持ち込み禁止となっている代表例としては、以下のようなものが挙げられます。
麻薬・覚醒剤などの違法薬物
電子タバコ(VAPEを含む)およびその付属品
猥褻な書籍・映像・雑誌など
偽ブランド品(商標権を侵害する製品)
仏像や仏教関連の宗教的美術品(大きさによって制限あり)
特に注意したいのが電子タバコ(VAPE)です。日本や他国では問題なく使用されている製品であっても、タイでは所持しているだけで処罰の対象となる法律があります。空港の税関で見つかった場合、没収はもちろん、罰金が科されるケースも報告されています。
また、制限付きで持ち込みが許可されている品も存在します。たとえばアルコール飲料は1人あたり1リットルまで、タバコは200本(1カートン)までとなっており、それを超えると没収または関税対象になります。
加えて、動植物や加工食品にも注意が必要です。特定の種子や肉製品、乳製品などは、検疫の対象となるため、持ち込む際には検疫証明書が求められることがあります。旅行や赴任のついでに持ち帰ろうと考える人も多いですが、禁止リストに該当する場合には没収の対象です。
このように、タイの入国審査は日本とは異なるルールが多いため、持ち込む物のリストを一度整理し、危険物・禁止物に該当しないかを確認することが不可欠です。荷造りの際には、内容物を把握しやすいようラベルやパッケージを残したままにしておくと、税関での確認もスムーズになります。
タイ出国カード・入国カードの書き方ガイド
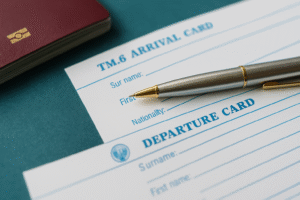 タイへの渡航時には、入国審査時に「入国カード(Arrival Card)」、出国時には「出国カード(Departure Card)」の提出が必要です。近年は一部の空港でデジタル化が進んでいますが、原則として紙のカードが必要とされているケースも多いため、基本的な書き方を知っておくことは重要です。
タイへの渡航時には、入国審査時に「入国カード(Arrival Card)」、出国時には「出国カード(Departure Card)」の提出が必要です。近年は一部の空港でデジタル化が進んでいますが、原則として紙のカードが必要とされているケースも多いため、基本的な書き方を知っておくことは重要です。
出入国カードは、飛行機内で配布されるほか、空港のイミグレーション手前にも用意されています。英語で記載する形式ですが、記入欄はそれほど多くないため、落ち着いて対応すれば心配はいりません。
まず「入国カード(Arrival Card)」には、以下のような情報を記入します。
フルネーム(パスポートと同じスペル)
国籍
パスポート番号
搭乗便名(例:JL31)
職業(例:Company Employee)
滞在先住所(ホテル名やコンドミニアム名)
滞在目的(例:Tourism、Business)
入国日
出発地(例:JAPAN)
「出国カード(Departure Card)」は、入国時に入国カードと一緒に提出するか、パスポートにホッチキスで留められて返される形式が一般的です。これは、出国時に再び提出する必要があるため、滞在中は必ず保管しておいてください。
出国カードに記入する内容も、氏名やパスポート番号、搭乗便など基本情報が中心です。特別な記述を求められることはありませんが、書き損じがあると手続きに時間がかかることがあります。
なお、観光ビザでの入国や短期滞在であっても、これらの書類が正しく提出されていない場合、入国審査や出国手続きがスムーズに進まないこともあります。記入欄に空欄がある、字が読みにくい、スペルミスがある、といった小さなミスがトラブルの原因になるため、記入後は必ず見直すようにしましょう。
こうして事前に記入例を把握しておけば、空港で慌てることなくスムーズに手続きを進めることができます。特に初めてタイを訪れる方は、現地の入国・出国カードの存在を見落としがちなので、旅前にしっかり準備しておくと安心です。
荷造り前に確認すべき注意ポイント
 タイへの渡航準備を進める中で、荷造りは避けて通れない大切な工程です。持っていく物の選定も重要ですが、それ以上に大切なのが「出発前に確認すべき注意点」をしっかり把握しておくことです。ここで抜けや見落としがあると、入国時のトラブルや現地生活での不便につながる可能性があります。
タイへの渡航準備を進める中で、荷造りは避けて通れない大切な工程です。持っていく物の選定も重要ですが、それ以上に大切なのが「出発前に確認すべき注意点」をしっかり把握しておくことです。ここで抜けや見落としがあると、入国時のトラブルや現地生活での不便につながる可能性があります。
まず確認すべきは、持ち込み制限や禁止品のルールです。アルコールは1リットルまで、タバコは200本までと制限があるほか、電子タバコや偽ブランド品、わいせつ物などはタイでは法律で禁止されています。これらは持っているだけで処罰の対象になるため、内容物をチェックしながら慎重にパッキングを進めることが大切です。
次に注意したいのが、電圧と変圧器の問題です。タイの電圧は220V、日本は100Vと大きく異なります。変圧器なしで使用すると故障や火災のリスクがあるため、必要に応じて変圧器や海外対応の製品を用意しましょう。特に日本から持って行く家電類には対応電圧が記載されているので、事前に確認しておくと安心です。
また、手荷物と預け荷物の区別も重要です。例えばパソコン、カメラ、貴重品や現金、常備薬などは機内に持ち込む必要があります。一方、液体物や刃物類は預け荷物に入れる必要があるため、それぞれのルールを航空会社の公式情報で再確認しておくとよいでしょう。
さらに、必要書類の準備も荷造りと並行して進める必要があります。パスポート、ビザ関連書類、入国カード、予防接種証明書(必要な場合)などは、すぐに取り出せる場所にまとめておくと空港でスムーズに対応できます。デジタル化が進んでいるとはいえ、紙ベースの控えを持っておくと万が一の際に安心です。
最後に、重量制限の確認を忘れずに行いましょう。航空会社ごとに預け荷物や機内持ち込み荷物の制限は異なります。超過すると追加料金が発生するため、荷物の重さは事前に計量しておくことをおすすめします。軽量化のために衣類や雑貨の一部を圧縮袋に入れるなどの工夫も有効です。
こうして事前に必要なチェック項目を押さえておくことで、当日の混乱を防ぎ、よりスムーズに渡航することができます。荷造りはただの作業ではなく、海外生活の第一歩を成功させるための準備段階だと意識して取り組みましょう。
タイ 移住 必需品を整理して理解するための総まとめ
- 日本の常備薬は効果や成分面で信頼性が高く安心できる
- 無添加調味料や白だしは現地で代用が難しいため持参が無難
- 日本製のラップやスポンジは品質が高く使い勝手が良い
- 水に流せるおしりふきや除菌ティッシュはタイでは手に入りにくい
- タイの生理用品は品質差があるため使い慣れた日本製が快適
- アルコール飲料の持ち込みは1リットルまでと明確に制限されている
- 入国時には20,000バーツ相当の現金を携帯していると安心
- 電子タバコや偽ブランド品などはタイへの持ち込みが法律で禁止されている
- 入国カードと出国カードは手書きで正確に記入する必要がある
- ビザなし観光でも荷物検査や所持金確認のリスクがある
- 日用品の中でも歯ブラシや洗剤は日本製を持ち込むと便利
- 子ども用の文房具や教材は日本で調達しておくと教育面で役立つ
- タイでは冬服が必要な場面もあるため羽織ものを1~2枚用意したい
- 電圧の違いにより家電は変圧器なしでは使用できないものが多い
- 荷造りの際は航空会社の持ち込み制限や重量に細心の注意が必要
いかがでしたでしょうか?タイ移住をスムーズに始めるためには、現地での生活環境を正しく理解し、自分にとって本当に必要なタイ移住必需品を見極めることが大切です。日本から持って行くべきもの、現地で代用できるもの、持ち込み制限や入国時の注意点など、あらかじめ情報を把握しておくことで、余計なトラブルや無駄な出費を避けることができます。この記事が、あなたの新しいタイ生活の第一歩を後押しするきっかけになれば幸いです。
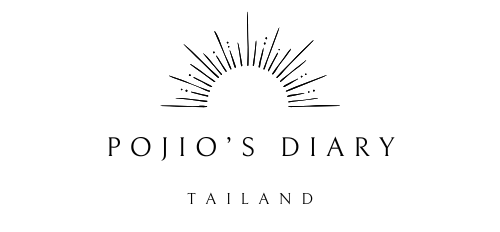

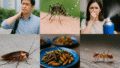

コメント