タイへの駐在が決まったご家庭にとって、子育ては大きな関心事のひとつです。特に、子どもの学校選びや生活環境、医療事情など、国内とは異なるさまざまな要素を事前に把握しておくことが、安心して新生活をスタートさせるための鍵になります。
本記事では、タイ駐在時の子供の学校の選び方を中心に、インターナショナルスクールや日本人学校、さらにはローカルスクールとは何か?といった疑問にも丁寧に答えていきます。また、高校生の進路選択や日本との違い、学校給食の実態など、タイ独自の教育事情についても具体的に解説します。
さらに、子育て費用や子育て支援の実情、病院の選び方、子育てアプリの活用方法など、暮らしに密着した情報も多数掲載。タイならではのメリットや子育てが楽になる工夫についても取り上げています。
これからタイでの駐在生活を始める方にとって、実用的な子育てハンドブックとしてお役立ていただける内容を網羅しています。初めての海外子育てに不安を感じている方も、このガイドを通して自信を持って準備を進めていただければ幸いです。 もうすぐタイ旅行!必需品リストはこちら
- タイでの学校の種類や選び方
- 子育てにかかる費用と支援制度の実情
- 医療機関の選び方と子どもの健康管理
- タイ独自の教育環境や生活上の注意点
タイ 駐在 子育ての基本と注意点
-
タイ駐在での子供の学校の選び方とは
-
タイのローカルスクールとは何ですか?
-
インターナショナルスクールの特徴と注意点
-
高校生の進学先と学校選びのポイント
-
子育て病院の選び方と医療事情
タイ駐在での子供の学校の選び方とは

タイ駐在に伴い、お子さんの学校選びは家族にとって非常に大きな決断となります。教育内容はもちろんのこと、言語環境、通学距離、将来の進学先、子どもの性格や適応力など、多角的に検討する必要があります。
まず、多くの日本人家庭が候補に挙げるのが「インターナショナルスクール」と「日本人学校」です。インターナショナルスクールは、英語などの外国語を主な授業言語とし、グローバルな教育カリキュラムを採用しています。一方、日本人学校は、日本の文部科学省の指導要領に準拠しており、日本と同様の教育がタイでも受けられるため、帰国後の編入や受験にもスムーズに対応できます。
どちらを選ぶべきかは、ご家庭の教育方針やお子さんの将来像によって変わってきます。たとえば「英語を早い段階で習得させたい」「国際的な感覚を養いたい」という方針であれば、インターナショナルスクールが向いています。逆に「将来的には日本の高校や大学への進学を考えている」「日本語でしっかり基礎学力をつけさせたい」という場合は、日本人学校を選ぶのが無難です。
加えて、通学の利便性も無視できません。バンコクなど都市部では交通渋滞が非常に激しく、登校・下校に予想以上の時間がかかることもあります。スクールバスの有無や、送り迎えの必要性も事前に確認しておくと安心です。
また、学校によっては入学試験や面接が実施されるため、事前の準備が必要になるケースもあります。定員の都合で希望する学校に入れないこともあるため、候補を複数用意し、見学や説明会への参加も検討すると良いでしょう。
このように、学校選びは単なる学力の問題だけでなく、生活全体に関わる重要な選択です。お子さんの性格や家庭の教育方針を踏まえ、将来を見据えたうえで慎重に検討することが求められます。
タイのローカルスクールとは何ですか?
 タイのローカルスクールとは、タイ国内の公立・私立を問わず、タイ語を主言語として教育を行っている現地の小学校のことを指します。タイ人の子どもたちが日常的に通っている、いわば「一般的な小学校」です。
タイのローカルスクールとは、タイ国内の公立・私立を問わず、タイ語を主言語として教育を行っている現地の小学校のことを指します。タイ人の子どもたちが日常的に通っている、いわば「一般的な小学校」です。
このローカルスクールの最大の特徴は、教育がすべてタイ語で行われる点にあります。教科書や授業内容、生活指導まですべてがタイ語で進められるため、言語が堪能でない外国人の子どもにとっては、かなり高いハードルとなります。特に初等教育の段階では、語学力が学習意欲や理解力に大きな影響を与えるため、無理に通わせることがかえってストレスになる場合もあります。
ただし、現地社会に溶け込みたい、もしくはタイ語を積極的に習得させたいという家庭にとっては、良い選択肢になることもあります。ローカルスクールでは、現地の子どもと同じ環境で生活することになり、文化や価値観を肌で感じることができます。実際、親の駐在期間が長期に及ぶ予定である場合や、すでにタイ語に親しんでいる子どもであれば、適応しやすい傾向があります。
ただ、外国人向けのサポート体制は限定的です。日本語や英語を話せる教員はほとんどいないため、保護者が言語面や学習面で継続的にサポートできるかが重要なポイントとなります。また、入学手続きや校則も学校ごとに異なり、行政的な書類のやり取りが必要な場合も多いため、事前調査は欠かせません。
このように、タイのローカルスクールは、文化理解や語学習得の面では非常に魅力的ですが、言語の壁やサポート体制の限界などを理解したうえで慎重に検討する必要があります。
インターナショナルスクールの特徴と注意点
 インターナショナルスクールは、タイ国内において外国人家庭に人気の高い教育機関の一つです。授業は主に英語で行われ、カリキュラムはアメリカ式、イギリス式、IB(国際バカロレア)など、さまざまな国際教育プログラムに基づいています。
インターナショナルスクールは、タイ国内において外国人家庭に人気の高い教育機関の一つです。授業は主に英語で行われ、カリキュラムはアメリカ式、イギリス式、IB(国際バカロレア)など、さまざまな国際教育プログラムに基づいています。
このような学校の最大の魅力は、グローバルな教育環境の中で学べる点にあります。多国籍の子どもたちと一緒に学ぶことで、異文化への理解が自然と育まれます。また、英語力が飛躍的に伸びる傾向にあるため、将来的に海外の大学や国際的なキャリアを視野に入れるご家庭には最適です。
さらに、設備面や教育サービスの質が高いことも特徴です。少人数制の授業、豊富な課外活動、最新のICT教材など、子どもたちの学びを多方面から支援する体制が整っています。教員の多くは外国人で、教育経験が豊富なプロフェッショナルである点も安心材料の一つでしょう。
一方で、いくつかの注意点もあります。最も大きいのは「費用負担」です。学費は年間で数十万バーツに上ることが一般的であり、日本円に換算すると100万円を軽く超えることもあります。入学金や施設使用料、スクールバス代などが別途必要なケースも多く、駐在手当などで会社が費用をカバーしてくれない場合は、家計への影響が大きくなります。
また、学校によって教育の質や方針には差があるため、名前や立地だけで決めるのは避けたいところです。学力の評価方法、補習の有無、進学実績などを具体的に確認し、お子さんの個性に合った学校を選ぶことが大切です。
このように、インターナショナルスクールは魅力的な選択肢である反面、金銭面や教育内容に対する理解と準備が必要不可欠です。事前に見学を行い、教師や在校生の様子を直接見ることで、学校との相性を見極めるようにしましょう。
高校生の進学先と学校選びのポイント
 タイに駐在する家庭にとって、高校生の教育環境は非常に重要な課題です。中学生までの教育と異なり、高校生の学びは大学進学や将来の進路に直結するため、学校選びに際してはさらに慎重な判断が求められます。
タイに駐在する家庭にとって、高校生の教育環境は非常に重要な課題です。中学生までの教育と異なり、高校生の学びは大学進学や将来の進路に直結するため、学校選びに際してはさらに慎重な判断が求められます。
タイ国内にはいくつかの選択肢がありますが、多くの駐在家庭が検討するのは、日本人学校の高等部(バンコク日本人学校には高等部は存在しないため、オンライン日本の高校や通信制高校を含む)、インターナショナルスクール、またはオンライン教育との組み合わせです。
インターナショナルスクールでは、世界標準のカリキュラム(IB、IGCSE、APなど)に基づいた授業が展開され、英語での大学進学を目指す場合に適しています。英語力に加えてプレゼンテーション能力や論理的思考なども評価されるため、日本とは異なる形での「学力」が問われることになります。
一方で、日本の大学への進学を視野に入れる場合、日本の教育課程を踏襲した通信制高校を併用するケースも見られます。最近では、タイに居ながらオンラインで日本の高等教育を受けられる制度も整ってきており、柔軟な学習スタイルが可能になってきました。
ただし、進学先によっては在学中に帰国して本格的に受験対策をする必要があることも考慮しておかなければなりません。また、海外大学への出願にはTOEFLやSATなどの試験が必要となるため、学校だけでなく予備校やオンライン講座を併用する必要も出てきます。
こうして見ると、高校生の学校選びは多くの選択肢と課題が複雑に絡み合っています。どの進路を選ぶにしても、親子でよく話し合い、将来のキャリアや学習スタイルに合った道を選ぶことが求められます。まずは各校の見学やカリキュラムの比較から始めると良いでしょう。
子育て病院の選び方と医療事情
 タイで子どもを育てる際、医療体制が整っているかどうかは大きな不安材料になるかもしれません。ただ、実際のところバンコクを中心とした都市部には、外国人向けの高品質な医療機関が数多く存在しており、子育て世帯にとって安心できる環境が整っています。タイ駐在の生活はこちらをご参考ください
タイで子どもを育てる際、医療体制が整っているかどうかは大きな不安材料になるかもしれません。ただ、実際のところバンコクを中心とした都市部には、外国人向けの高品質な医療機関が数多く存在しており、子育て世帯にとって安心できる環境が整っています。タイ駐在の生活はこちらをご参考ください
特に日本人家庭に人気なのが、サミティベート病院(スクンビット49)やバンコク病院、日本語通訳付きの国際病院です。これらの病院では、日本語で診察を受けられるだけでなく、医療水準も非常に高いため、初めての海外生活でも安心して子どもの健康管理を任せることができます。
一方で、タイには公立病院やローカルクリニックも多く存在します。費用は非常に安く済む一方で、言語の問題や待ち時間、衛生面などに不安を感じる方もいるかもしれません。したがって、日常の診療や予防接種、急病時の受診先などは、あらかじめ信頼できる病院を決めておくことが重要です。
また、タイの医療保険事情にも目を向けておきましょう。現地採用の駐在員の場合、保険の範囲が限られていることもあり、子どもに必要な予防接種や健診が対象外になるケースもあります。海外医療保険に加入しておくことで、急な入院や治療費の自己負担を減らすことが可能になります。
なお、子どもの急病やケガに備えて、夜間や休日にも対応してくれる医療機関の情報を常に把握しておくことも大切です。病院までの距離や交通手段も、物件選びの際に考慮すべきポイントになります。
このように、タイの医療事情は日本と比べて異なる点が多いものの、しっかりと準備をすれば安心して子育てを進めることができます。現地の病院情報を集め、適切な医療体制を整えることが、家族の安心につながります。
タイ 駐在 子育てに役立つ生活情報
-
子育ての費用はどれくらいかかる?
-
子育て支援制度やサービス事情
-
学校給食の内容と日本との違い
-
子育てが楽になる便利グッズと環境
-
子育てハンドブックの活用法
子育ての費用はどれくらいかかる?
 タイで子育てをする際の費用は、生活スタイルや学校の選択によって大きく異なります。物価が日本より安いという印象を持たれがちですが、実際には「教育」「医療」「日用品」の3分野に関しては、駐在家庭であってもそれなりの出費が発生することを想定しておく必要があります。
タイで子育てをする際の費用は、生活スタイルや学校の選択によって大きく異なります。物価が日本より安いという印象を持たれがちですが、実際には「教育」「医療」「日用品」の3分野に関しては、駐在家庭であってもそれなりの出費が発生することを想定しておく必要があります。
まず教育費ですが、インターナショナルスクールに通わせる場合は、年間で100〜300万円程度が一般的です。入学金や教材費、制服代、スクールバス代などが加わると、さらに費用は増えます。幼稚園から高校までこの水準が続くことを考えると、教育費は子育て全体の中でも最も大きな負担となります。
一方で、日本人学校を選択する場合は、授業料や諸費用を含めても比較的安価に収まる傾向があります。ただし、日本語補習校や通信教育、塾の利用などに費用がかかることもあり、総額では予想より高くなることもあります。
医療費については、私立の国際病院で診察を受けると1回の受診で1,000〜3,000バーツ(約4,000〜12,000円)程度が一般的です。保険でカバーされる場合もありますが、予防接種や健診などは自己負担となることが多く、事前に補償内容を確認しておきたいところです。
また、生活費や日用品に関しては、ローカルな生活スタイルを取り入れればかなり節約できます。例えば、屋台の食事や地元のマーケットを活用すれば、1ヶ月の食費を抑えることが可能です。ただし、日本と同じ品質やサービスを求めると、むしろ割高になる場合もあります。
たとえば、オーガニック製品や日本製の育児用品は、現地では高価に設定されていることが多いため、必要に応じて日本からの持ち込みを検討する家庭もあります。
このように、タイでの子育て費用は「選び方次第」で大きく変動します。必要なものと不要なものを明確にし、優先順位をつけて生活設計を行えば、コストを抑えながらも充実した子育てを実現することができます。
子育て支援制度やサービス事情
 タイにおける子育て支援制度は、日本のような行政主体の仕組みとは異なる部分が多く、主に民間サービスや地域のネットワークを活用する形で構築されています。そのため、駐在家庭が期待する「公的支援」ではなく、「民間による柔軟なサービス提供」が中心になると理解しておくとスムーズです。
タイにおける子育て支援制度は、日本のような行政主体の仕組みとは異なる部分が多く、主に民間サービスや地域のネットワークを活用する形で構築されています。そのため、駐在家庭が期待する「公的支援」ではなく、「民間による柔軟なサービス提供」が中心になると理解しておくとスムーズです。
たとえば、バンコクなどの都市部では、民間企業や日系団体による育児サポートサービスが充実しています。ナニー(住み込み・通いのベビーシッター)やハウスキーパーの雇用は非常に一般的で、家事や育児の負担を大きく軽減できる仕組みが整っています。日本では高額になるこうしたサービスも、タイでは比較的リーズナブルに利用可能です。
また、日系のナーサリー(保育園)や一時預かり施設も多数存在し、日本語に対応している施設も増えています。奥様会や地域のママグループなどによる情報共有も活発で、そうしたつながりを通じて信頼できる施設や人材を見つけるケースも多く見られます。
一方で、日本のように全国一律の子育て手当や自治体による支援制度が整っているわけではありません。そのため、予防接種費用や育児用品購入の助成といった支援を期待する場合は、日本側の制度(児童手当など)を海外転出後も受けられるかどうかを個別に確認する必要があります。
このように、タイでの子育て支援は「制度による補助」ではなく、「サービスによる実用的な支え」が中心です。公的制度が限定的である一方、民間の支援環境が豊富に整っているため、現地情報を積極的に集めながら、家庭ごとに合った支援の形を見つけていくことが重要です。
学校給食の内容と日本との違い
 日本の学校給食は、栄養バランスが考慮されており、全国的に一定の基準に基づいた内容が提供されています。子どもの成長を支えるうえで欠かせない制度として、高く評価されている取り組みです。
日本の学校給食は、栄養バランスが考慮されており、全国的に一定の基準に基づいた内容が提供されています。子どもの成長を支えるうえで欠かせない制度として、高く評価されている取り組みです。
一方で、タイでは学校給食の運用方法が施設によって大きく異なります。公立学校では簡易的な給食が提供されることもありますが、予算や設備の関係でメニューが限定的だったり、栄養バランスが不十分だったりすることも少なくありません。
特にインターナショナルスクールでは、給食がオプション制となっているケースが多く、学校が契約しているケータリング業者が日替わりでランチを提供するスタイルが一般的です。内容は洋食が中心で、パスタ、グリルチキン、フルーツなど、いわゆる「子どもが好みやすいメニュー」が選ばれている傾向があります。
ただし、学校によってはアレルギー対応が限定的だったり、宗教や文化的背景を考慮した特別食の用意が難しいこともあるため、事前確認が必要です。また、ランチを持参する家庭も多く、手作り弁当やレトルト食品を活用して個別に食事管理をする例も増えています。
タイのローカルスクールでは、校内の売店や屋台で食事を購入する形態もあり、子どもが現金で自由に食べ物を買うというスタイルも一般的です。その場合、味付けが濃い・甘い・油っぽいといったメニューも多く、日本人家庭では「健康面に不安がある」としてお弁当を持参させることも珍しくありません。
このように、日本の学校給食と比べて、タイでは「給食はあって当然」という制度ではなく、「選択肢の一つ」という扱いであることが多いです。家庭の方針やお子さんの健康状態に応じて、食事の形式を柔軟に選べる環境が用意されていると考えると良いでしょう。
子育てが楽になる便利グッズと環境
 タイでの子育てを快適にするには、現地の環境に合った便利グッズや生活の工夫を上手に取り入れることが鍵になります。特に日本から持ち込むもの、現地で調達できるものの違いを把握しておくと、引っ越し後の生活もスムーズに始められます。
タイでの子育てを快適にするには、現地の環境に合った便利グッズや生活の工夫を上手に取り入れることが鍵になります。特に日本から持ち込むもの、現地で調達できるものの違いを把握しておくと、引っ越し後の生活もスムーズに始められます。
まず、タイの気候は高温多湿であるため、日本と同じ育児用品では対応が難しい場面があります。例えば、汗をかきやすい子どもには通気性の良い肌着や速乾性の高い衣類が必須です。また、蚊が多い地域では蚊帳や虫よけグッズが非常に役立ちます。日本製の低刺激な虫よけスプレーや、電池式の蚊取り機器は現地で手に入りにくいため、あらかじめ持参しておくと安心です。
一方で、タイには子育てを支える便利なサービスも充実しています。ネットスーパーの宅配サービスや、モバイルアプリを使った家事代行、育児用品のオンライン注文など、日本と遜色ない利便性を感じられる場面も少なくありません。例えば、GrabやLINE MANといったアプリを使えば、離乳食の材料やオムツなども自宅に届けてもらうことができます。
また、多くのコンドミニアムではファシリティが充実しており、プールやキッズルーム、遊具付きの共有スペースが設けられていることが一般的です。屋外で体を動かす機会が増えるため、体力が有り余る年齢の子どもには理想的な環境といえます。
ただし、現地での子育てに慣れるまでは、気候や文化の違いに戸惑うこともあるかもしれません。そうしたときには、現地在住のママ友グループやSNSを通じて情報交換をすることが大きな助けになります。実際の口コミから得られる情報は、生活の細かなストレスを軽減してくれるでしょう。
このように、タイでの子育てを楽にするためには、便利グッズや生活サービスの活用とともに、「現地の子育て環境に合わせた柔軟な対応力」がポイントになります。過度に完璧を求めすぎず、タイならではの良さを活かしながら、快適な育児生活を築いていきましょう。
子育てハンドブックの活用法

タイへの駐在が決まり、子どもを連れて海外生活をスタートさせる際、「何から準備を始めれば良いのかわからない」と戸惑う方は少なくありません。そんなときに心強い味方となるのが子育てハンドブックです。このハンドブックは、現地の子育て環境や制度、生活に必要な手続きなどが体系的にまとめられており、初めてのタイ生活における不安を大きく軽減してくれます。
多くの場合、日系大使館や日本人会、現地の日本人向けコミュニティなどが発行しており、情報の信頼性が高いのが特徴です。内容は、ビザの取得方法や医療機関の利用方法、学校の種類と選び方、日常生活に関わる買い物や公共交通機関の使い方まで、幅広い項目が丁寧に解説されています。特に子育て世帯にとっては、教育機関の情報や予防接種スケジュール、緊急時の連絡先といった実用性の高い項目が重宝されます。
こうしたハンドブックは、読み物として一度通読するだけではなく、「生活の辞書」として手元に置いておくと便利です。例えば、入園を検討している日本人幼稚園の一覧や、タイ語に不慣れな方向けの病院選びガイド、子どもが現地の環境に馴染むためのヒントなど、必要になったときにすぐ参照できる構成になっているものが多くあります。
また、最近ではPDF形式での配布や、スマートフォンで閲覧できるオンライン版も増えており、渡航前から情報収集を始めることも可能です。とくに駐在が初めてでタイの生活に不安を感じているご家庭にとって、信頼性のある一冊を持っているだけで精神的な安心感が違ってきます。
こうして見ると、子育てハンドブックは単なる情報冊子ではなく、新生活の基盤を築くための実践的なガイドブックです。渡航前の準備段階から日常生活に至るまで、必要な場面で繰り返し活用することで、子どもとの海外生活をよりスムーズに、そして安心して始めることができるでしょう。
いかがでしたでしょうか?タイ 駐在 子育ては、学校選びから医療体制、生活費や育児支援に至るまで、多くの準備と情報収集が求められる一方で、家族にとって貴重な体験と成長の機会にもなります。現地の文化や環境に柔軟に対応しながら、信頼できる教育機関や医療機関、便利な育児サービスを上手に活用することで、初めての海外生活でも安心して子育てができるはずです。タイならではの温かい人々や暮らしやすい環境を味方につけ、家族みんなで前向きに、新しい生活を楽しんでいただければ幸いです。
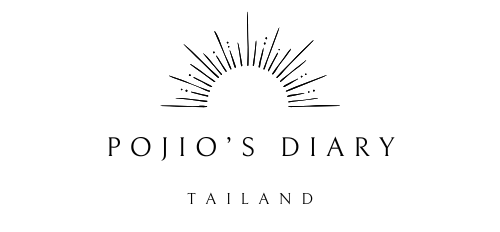


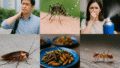
コメント